発達概念を巡る「普遍論争」と「カテゴリー錯誤」
普遍論争とは?
哲学、特に、形而上学(存在論)の分野で、歴史的に長く議論が継続している論題として、「普遍論争」というものがある。
この論争は、普遍的な存在というものは、本当に実在しているのかどうか、あるいは、そのような普遍的な存在というものは、そのような名称が付されているだけで、実在していないのではないかという論争だ。
普遍概念は実在しているとするのが実在論、名称だけだというのが唯名論だ。
こういった論争は必ずしも、西洋哲学の専売特許ではない。東洋思想、中でも古代中国の諸子百家の中の「名家」においても名実論という形で、存在していた問題だ(「白馬は馬かどうか」という禅問答のような話しとして知られているのではなかろうか)。
更にいうと、この論争は、生物学の分野で展開されている「種論争」という形で、アクチュアルな問題にも関連している。「種論争」とは、例えば馬という「種」について、一方では、「馬」という種が実在しており、赤兎馬やハイセイコーのような個々の馬はそのインスタンスに過ぎないという実在論的立場があり、他方で、「種」としての「馬」は、人の本質主義的思考に基づいて生み出されたいわば観念(幻想)であって、実際に存在するのは、赤兎馬やハイセイコーという個体としての馬でしかないという唯名論的立場の対立である。これは、進化生物学において、重要な問題であり、進化の単位が個体なのか、種なのかということで、進化のメカニズムの理解に差が出てくるからである。
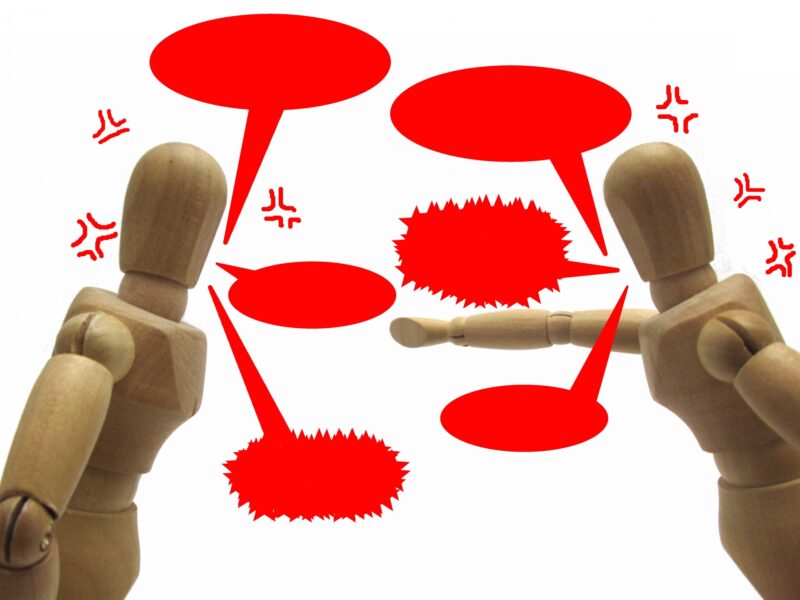
「発達」は、実在論的か唯名論的か?
なぜ、このような話しを持ち出したかというと、子どもの「発達記録」の分析をしていく中で、分析対象としている「発達(過程)」なるものが、実在するものなのかということが疑問に思えてきたからだ。
つまり、普遍論争的に言えば、「発達とは、子ども(又は人)に生じるある特定の属性を帯びた変化であり、そのような統一的に把握できる何かが実在する」という実在論と、「発達とは、子ども(又は人)が見せる変化の中から、便宜的に抽出された集合に付された名称であって、実際に分析の対象となる存在は、個々の変化である」という唯名論の、どちらなのだろうかという疑問が、私の中で形成されてきたからである。
ちなみに、現行の保育所保育指針では、「保育過程」という言葉が使われているが、発達がプロセスであるのであれば、変化の逐次的な継続(流れ)に「発達過程」という名称を付けているということであり、個々の資質や能力の発現とは別の「発達するもの」というものが存在しているということになるのではなかろうか(実在論的発想)。となると、そのような理解の元で実施すべき分析の対象は、そのプロセスを生み出す「何」であろう。
要すれば、「発達(過程)」を実在論的に考える場合には、発達の「本質」があって、個々の資質や能力の発現は、インスタンス(実例)ということになる。分析の究極的な対象は、その「本質」ということになる。問題は、その「本質」とは、何なのかということだが、それは良く分からない。
先ほどの「種論争」の中の種不在論の説明において、「幻想」という言葉を使った。これは、種実在論の背景には、心理的本質主義(物事には共通する本質的要素が実在していると考えがちな、人間の思考の癖)があることに対する批判的姿勢があるからである。
同様に、「発達」という概念に対しても、人は、何か「発達の本質」のようなものを、子どもの中にアプリオリに措定してしまっているだけかも知れないという危惧を抱いてしまっているところだ。
唯名論的に「発達」を考えると??
心理的本質主義による「誤謬」を回避しようとすると、「発達」という存在は、実在せず、唯名論的存在として、検討してみる必要があるということになる。
その場合には、実際に存在しているのは、「字が書ける」「数字が分かる」「トイレに自分で行ける」「友だちの言い分を聞くことができる」等々の個別の資質や能力の達成/発現であり、発達はそれらの個々の存在をまとめる「レッテル」ということになる。
ここで問題となるのは、「発達」として、常識的に括り出される人間の変化と、それ以外の人間に生じる様々な変化-例えば、病気、怪我、趣向の変化、加齢-との関係だ。
唯名論的に「発達」を考えるとすると、様々な人間の行動変容を何らかの対象/要素の全体から、「便宜的」にくくりだしているに過ぎないということになるのだから、「発達」以外の様々な変容との分別をどうするのかということが、問題としてせり上がってくる。
従前行われたことのなかった、某かの行動を取るようになるという事象には、様々な直接的要因が考えられるが、それが機械的な外力による強制でないかぎり、脳神経的作用の結果であることは、現代の自然主義的哲学や心理学、生理学の元では認められることであろう。つまりは、象徴的に言えば「シナプス結合」の変化が、行動変容となって現れるということになる。
となると、「発達」という現象と、病変、怪我、あるいは感覚刺激の結果としての趣向や関心の変化、さらには加齢によって生じる脳神経の変容、そしてその結果としての行動変容とは、「シナプス結合」の変化というグラデーションの中にあるものと捉えることができてしまう。
先に紹介した「種論争」とは、遺伝的変異のグラデーションの中で、どこかに線を引いて「種」と認識することができるのかという問題でもあったが、行動変容をもたらす「シナプス結合」の変容のグラデーションの中の、どこからどこまでを「発達」とするかというのは、所詮、定義次第、便宜的なものでしかないということもできる。
特に、脳神経科学の進展により、「シナプスス結合」の量は、出生後急速に増加するが、比較的短時間に「刈り込み」が生じ、成人期には、半分になる部分もあるということが分かってきており、「シナプス結合」の量と能力の多寡の関係は単純ではないことが分かってきているので、なおさらだ。
「発達」という「カテゴリー錯誤」
そもそも、「発達」の理解の仕方に、「カテゴリー錯誤」があるのではなかろうか。
「カテゴリー錯誤」とは、ある概念や存在を、本来、その概念や存在が持ち得ない性質を持つ概念や存在に分類し理解してしまう、人間の誤解の1つの形のことだ。このような人間の誤解のパターンを論じた哲学者が用いた例では、「大学」を知るために、教室や図書館、研究室といった建物によって代表させる、表象させるのは、一種の比喩であり、「建物」の集合で「大学」を理解しようとすることが「カテゴリー錯誤」ということになる。
「カテゴリー錯誤」とは、個々の建物という存在と、大学とは、存在のレベルが異なっており、「大学」を理解するためには、大学という「機能」が社会全体の中で果たしている役割を理解しなければならず、探求の方向が間違っていることを認識させてくるものだ。
同様に、字が書ける、鉄棒ができる、友だちの心の内容を想像できるという個々の事象の集合を、「発達」と理解してしまうことは、「カテゴリー錯誤」の陥穽に陥っているのではなかろうかという不安が、私にはある。
「発達」を個々の資質や能力の達成や発現の集積として理解すべきではなく、人間あるいは生物の「進化的に到達した生存のあり方」に対して果たしている何らかの価値や機能という方向から理解するということもあるべきなのではないかと思っている。
そのような発想からは、そもそもなぜ、あるタイプの生物は、生まれた瞬間に、必要な機能を全て実装しておらす、「発達」「成長」しなければならないのかという問題の切り口を設定することができる(単細胞生物には、恐らく発達が概念できない)。
現在、生物の進化という観点から、「なぜ病気が生じるのか」を探求する進化医学という研究分野がある。進化という淘汰、適応のプロセスからすると、病気になるような要素はなくなっていくはずであるが、なぜ生物、特に人間は、いまだに病気になるのかということを理解し、そこから新しい発想で、治療法を解明しようというのが、この研究分野の動機だ。
「発達」についても、個々の行動変容からは理解できないであろう「生物の生存にとっての意義」という観点から、「カテゴリー錯誤」に陥らないような探求の方向性が必要なのではないだろうか。
まとめ
「発達」にも人の進化的適応に則して発現する何か本質的なメカニズムが体内に存在していると実在論的に考えるのか、それとも、「発達」とは人の適応的変容のうちの特定部分を便宜的に切り出しているものだと唯名論的に考えるのか?
どちらの研究方略でいくことが、「カテゴリー錯誤の陥穽」を回避することになるのか、引き続き、検討を深めていきたいと思っている。
<関連エントリー>
